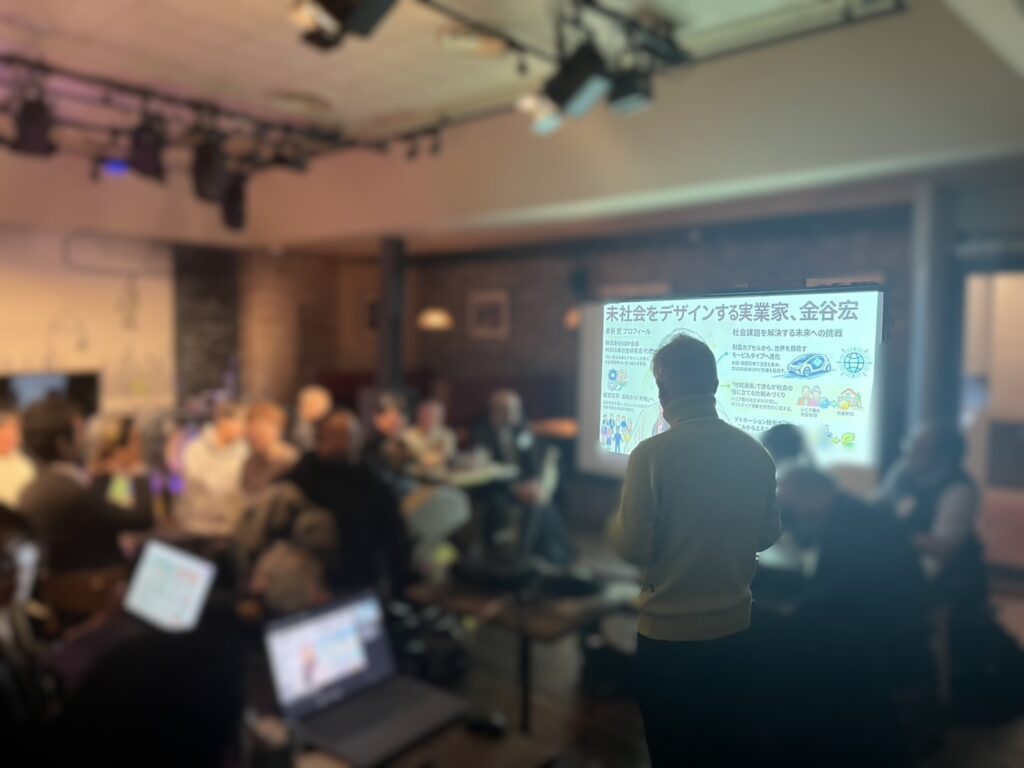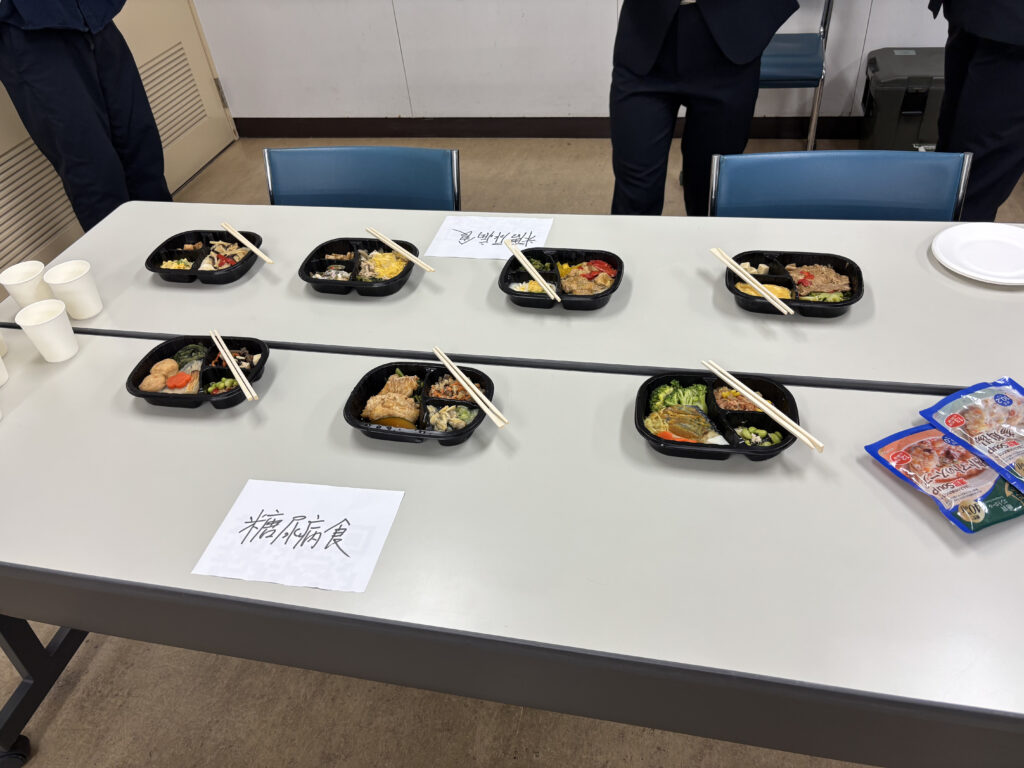私達、一般社団法人 社会課題解決支援協会(以下、社課)は、内閣府実証事業として
「官民連携による避難所運営の質の向上強化事業」
を、大阪府大東市(市街地モデル)・三重県紀北町(過疎地モデル)にて実施いたしました。
本事業では、食物アレルギーや持病を持つ被災者が、避難所はもちろん、
在宅避難・車中泊など“指定避難所以外”の場所でも健康を損なわず生活できる環境づくり
を目的としています。
そのために、社課が提供する 「命のカルテ」 を中心とした
健康情報・地域連携システム(※1) と、
キッチンカーによる 温かい食事と医療供給(※2) を連携させる実証を行いました。
 実証で使用したキッチンカー
実証で使用したキッチンカー
事業全体の背景
災害時、避難所で提供される食事は“健常者向けの一般食”が中心であり、
糖尿病などの持病やアレルギーを抱える方々は、
- 食べられるものがない
- 適切な食事が取れず体調悪化につながる
- 必要な薬や医療支援が届かない
- 在宅避難や車中泊では「支援対象にすらならない」
といった深刻な課題を抱えています。
社課はこの問題を解決するため、
「誰に、どのような食事と医療を届けるべきか」を可視化し、
かつ被災者へ“届けられる仕組み”の構築
を目指して本事業を実施しました。
(※1)健康情報・地域連携システム(命のカルテ)とは
- “どこに、どんな人が、どんな健康状態で避難しているか”を即時に把握
- 持病・服薬・アレルギー等の情報を自治体・支援者が安全に共有
- 被災者の状態に合わせた
- 温かい食事
- 病態別食(腎臓食・糖尿病食等)
- アレルギー対応食を提供できる
災害時でも安心して 「健康を取り戻す食事」 を1人1人に提供できる仕組みです。
(※2)生命維持に係る食事と医療供給について
本事業では、キッチンカーに以下の機能を搭載し、
- 温かい食事の提供
- 病態食・アレルギー対応食の提供
- 薬剤師による服薬対応(大東市)
- オンライン診療の提供(紀北町)
を可能にする取り組みを行いました。
災害関連死の原因となる
低栄養・脱水・持病悪化・アレルギー発作
を防ぐための重要な取り組みです。
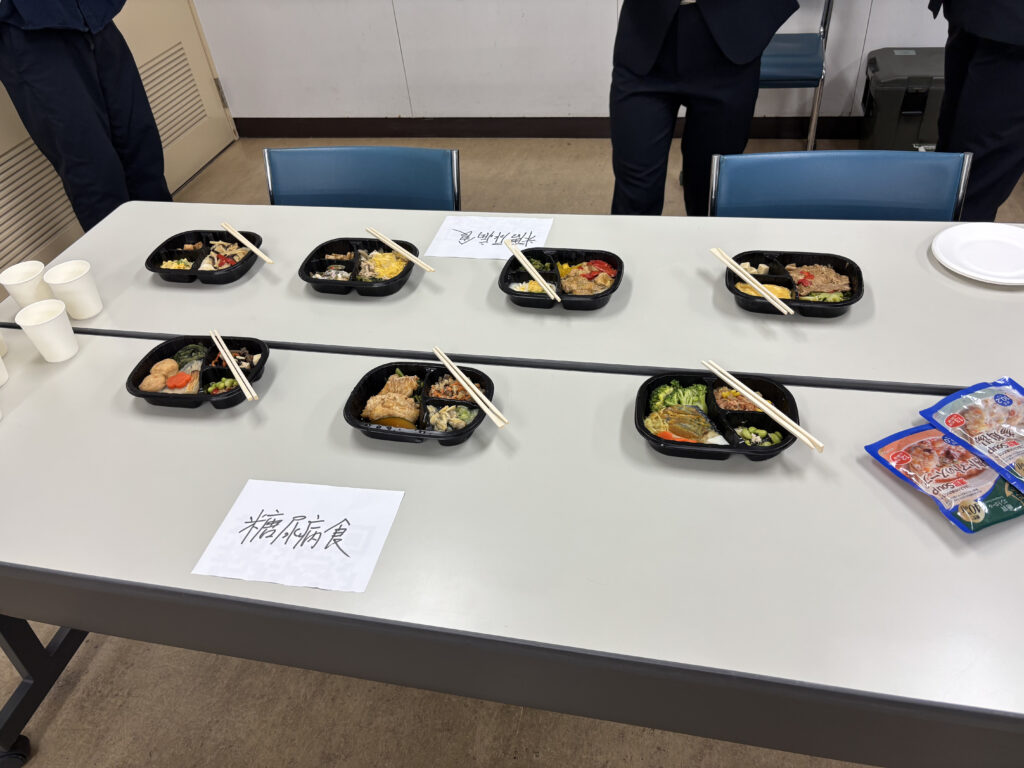 病態別食の試食
病態別食の試食
【紀北町モデル(過疎地を想定)】
“限界集落で災害関連死ゼロ”を目指す取り組み”
紀北町島勝区(高齢化率80%超の限界集落)では、
日常的なオンライン診療と健康情報システムの稼働 を活かし、
有事を想定した以下の取り組みを実施しました。
◆ 具体的な事業内容
① キッチンカーによる小回りの利く温かい食事提供
- 避難所だけでなく、
在宅避難者・車中泊者にも届けられる動線 を構築
- 持病に応じた食事提供をテスト
② オンライン診療の実施
キッチンカーに以下の機材を搭載し避難所外で医療提供を実現:
③ 住民参加型の炊き出し訓練と健康支援
炊き出し訓練に合わせて、命のカルテの情報を活用し、
“地元の誰にどんな食事が必要か”を確認しながら支援提供。
◆ 期待される効果
- 在宅避難・車中泊者も「支援対象」になれる
- 高齢者の健康維持に寄与
- 医療機関が遠い地域でも、オンライン診療で迅速に対応
- 災害関連死の大きな要因である「食の問題」を解消
 紀北町での実証の様子
紀北町での実証の様子
【大東市モデル(市街地を想定)】
“アレルギー・持病等による災害関連死ゼロ”を目指す取り組み**
市街地を想定した大東市では、命のカルテとキッチンカーを連動させ、
食事と医療を一体的に支援する体制構築 を目指しました。
◆ 具体的な事業内容
① 移動薬局車(ファーマシーカー)との連携
大東市が協定する
アクセスライフ社 × エースケータリング社の移動薬局車
と命のカルテを連携。
- アレルギー情報
- 持病・服薬情報
を即時に確認しながら、食事・薬を提供できる仕組みを構築。
② 薬剤師による支援
車両に薬剤師が同乗し、
被災者の健康状態をチェックしながら適切な食事・薬を提供。
 移動薬局車(ファーマシーカー)
移動薬局車(ファーマシーカー)
◆ 期待される効果
- アナフィラキシーなど“食のリスク”を大幅軽減
- 薬剤師によるケアで持病悪化を防止
- 避難所外の被災者も支援対象にできる
- 食事と医療の一体化により災害関連死の抑制効果
事業による成果目標
本事業の成果として、以下の点が確認されました。
- キッチンカー × 健康情報システムにより、
避難所・在宅避難・車中泊いずれにも食事と医療提供が可能であることが実証
- 持病・アレルギー情報を命のカルテで共有することで、
安心安全な食事の提供が可能になる
- 過疎地・市街地それぞれで、
今後のモデルとなる災害時対応の形を示すことができた
- 避難所の生活環境改善に向けた具体的な運用課題が明確になった
まとめ
今回の実証により、過疎地・市街地という異なる環境でも、
「命のカルテ」とキッチンカーを活用した
食事・医療支援の提供が十分に機能する ことが確認できました。
また、自治体・医療・民間企業・地域住民が連携することで、
災害時の弱者支援における新しいモデルケースを示すことができました。
社課は引き続き、
“災害関連死ゼロ”の社会の実現 に向けて、
全国の自治体と連携しながら取り組みを進めてまいります。
また、年末には社課の忘年会&交流会を行う予定ですので、
そのご報告に関しても、乞うご期待!